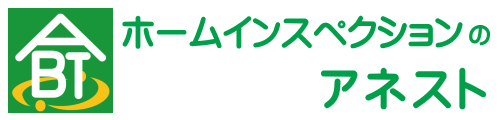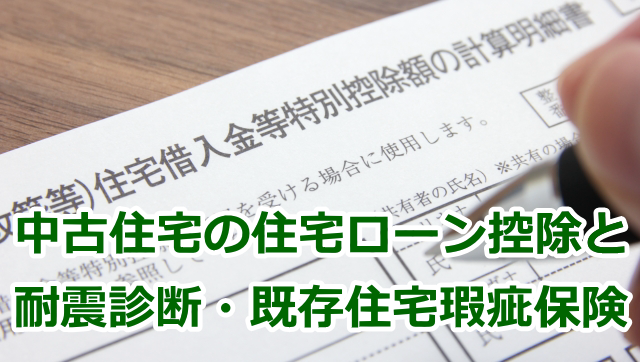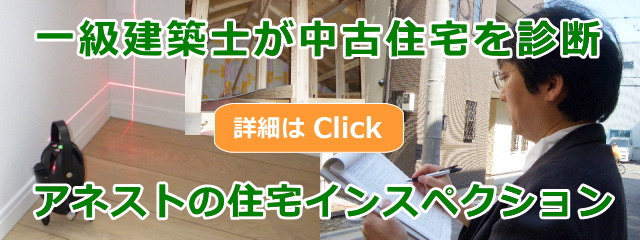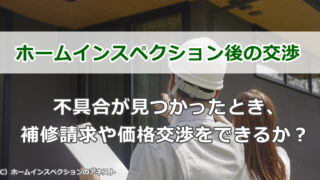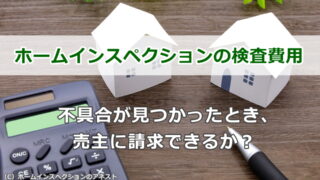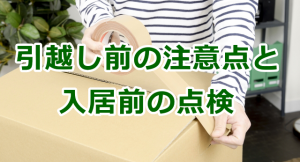中古住宅を購入するときに銀行等から購入資金の融資(住宅ローン)を受ける人は非常に多いですが、この場合、条件次第では所得税の控除を受けられるので、住宅を購入するならば、必ず知っておきたいものです。
本来ならば、不動産会社が住宅ローン控除について詳細を把握し、買主へ説明してあげたり、控除に必要なことを段取りしてあげたりすればよいのですが、残念ながら詳細を把握していない不動産会社やその営業マンが少なくないため、買主は自分でもよく調べておく必要があります。
ここでは、住宅ローン控除による減税というメリットを受けられずに損することのないように、中古住宅の買主が知っておくべきことを解説します。具体的な解決策も示しておくので活用してください。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、正確には住宅借入金等特別控除と言いますが、住宅購入の際には住宅ローン控除や住宅ローン減税という言葉が使われていることが多いです。これらは同じものです。
この住宅借入金等特別控除とは、住宅ローンを利用して住宅を新築・購入・増改築等をして、自己居住用に使用した場合に、住宅ローンの年末残高を基に計算した金額を所得税額から控除する制度です。
新築も中古住宅も対象となりますが、中古住宅には対象とならない物件も多いですので注意が必要です。後述する中古住宅の要件を確認してください。
中古住宅で住宅ローン控除を受けるには
※※※ 注意 ※※※
2022年(令和4年)度の税制改正により、後述する築年数の要件が撤廃になり、建物の登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であれば、新耐震基準に適合しているとみなして、住宅ローン減税を受けられる受けられることになりました。つまり、建築日付が昭和57年1月1日以降の住宅であれば、住宅ローン減税を目的とした耐震基準適合証明書や既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書は不要となります(追記:2022年4月1日)。
参照:2022年度の改正で住宅ローン控除の耐震基準適合証明書は必要なくなった?
中古住宅を購入して住宅ローン控除を受けるための要件を解説します。物件に関する要件とその他の要件があるため、その2つにわけて説明しています。
中古住宅の物件の要件
まずは、物件の要件について説明します。ややわかりづらいところもありますから、少し時間をかけて、確認しておきましょう。以下の4点のいずれにも該当する必要があります。
- 建築後、使用されたものであること
- 取得時に生計が同じで、取得後も生計が同じである親族等からの取得ではないこと
- 贈与による取得ではないこと
- 以下のA~Cのいずれかに該当すること
A:建築後20年以内に取得すること(マンション等の耐火建築物なら25年以内)※1,2
B:上の年数を超えるものでも、以下の3点のうちいずれかの書類があること
耐震基準適合証明書(家屋取得日の前2年以内に調査を終了したもの)
既存住宅売買瑕疵担保責任保険の付保証明書(家屋取得日の前2年以内に保険契約を締結したもの)
建設住宅性能評価書(耐震等級:1以上)(家屋取得日の前2年以内に評価されたもの)
C:取得日までに耐震改修を行うことを申請し、且つ、居住するまでに耐震改修工事を実施し、さらに耐震診断を行って耐震基準に適合することを証明すること
※1
耐火建築物とは、建物の登記簿の家屋の構造が鉄骨造や鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造になっているものです。他にも石造やれんが造、コンクリートブロック造も対象ですが、これらの構造で25年の要件を満たすものは非常に少ないです。
※2
軽量鉄骨造は耐火建築物ではないので注意が必要です(誤解する人が多いので要注意)。
その他の要件
物件の要件以外にも中古住宅で住宅ローン控除を受けるために必要な要件があるため、紹介しておきます。
- 取得日から6カ月以内に居住し、その年の年末まで居住していること
- 住宅ローン控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
- 対象物件の登記簿に記載の床面積(※)が50㎡以上で、その1/2以上が居住用であること
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
- 居住した年とその前後の2年(つまり合計5年間)に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと
※マンションの床面積は専有部分に限る。
年末時点で居住していないときや高所得の人、面積の小さな住宅は対象とならないようになっていますし、返済期間が短い場合も対象になりません。短期で返済予定であっても、借入期間は10年以上としておき、金利負担と減税メリットを比較しながら、途中で一括返済することも考えるとよいでしょう。
ちなみに、住宅ローン控除を受けるためには、確定申告が必要ですので忘れないようにしてください。
築20年超の木造・軽量鉄骨造の具体的な対応方法
前述のとおり、2022年(令和4年)度の税制改正により、建物の登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であれば、耐震基準適合証明書や既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書がなくても住宅ローン減税を受けられることになりました(追記:2022年4月1日)。
参照:2022年度の改正で住宅ローン控除の耐震基準適合証明書は必要なくなった?
前述したように、「建築後20年以内に取得すること(マンション等の耐火建築物なら25年以内)」という要件がありますが、これに該当しなくとも以下の3点のうち1つの書類を取得できれば、住宅ローン控除の対象となりえます。
- 耐震基準適合証明書
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険の付保証明書
- 建設住宅性能評価書
木造住宅や軽量鉄骨造なら築20年超、鉄骨造や鉄筋コンクリート造なら築25年超の場合に上の書類が必要だと覚えておくとよいでしょう。
この3点のうち現実的に取得を目指すことが多いのは、「耐震基準適合証明書」と「既存住宅売買瑕疵担保責任保険の付保証明書」の2つです。しかし、この2つなら容易に取得できるかといえばそういうわけでもありません。残念ながらいずれも現場検査や審査の結果、不適合となることの方が多いため、あきらめざるを得ない物件も多いです。
耐震基準適合証明書
耐震基準適合証明書とは、耐震診断を行って耐震基準に適合していることを確認することで発行してもらえる証明書です。
耐震診断は、基本的には木造住宅(型式適合認定の工法による建物を除く)で行うことができますが、鉄骨造や鉄筋コンクリート造(RC造)では対応が難しく、現実的にはこれらの工法の場合は次に紹介する既存住宅売買瑕疵担保責任保険を利用することが多いです。
多くの木造住宅の耐震診断をしてきましたが、実施しても不適合になる住宅は多いです。築年数が古いものほど、不適合になる確率が高く、築40年を超えた住宅で適合することはほとんどありません。但し、過去に耐震改修工事を実施している住宅であれば、可能性がありますので、診断業者に問合わせるとよいでしょう。
耐震診断の難しいところは、診断するために必要な図面を入手できないことが多いことです。売主が新築当時の設計図を保管しておればよいのですが、紛失等により保管していないことが多いです。稀に、新築した建築会社や設計事務所から提出してもらえることがあるので、念のために売主から聞いてもらうのも1つの方法です。
耐震基準適合証明書について、より詳しく知りたい人は「耐震基準適合証明書のメリットと取得の仕方と注意点」が参考になります。
既存住宅売買瑕疵担保責任保険の付保証明書
設計図がなく耐震診断をできない住宅や鉄骨造や鉄筋コンクリート造の場合、既存住宅売買瑕疵担保責任保険を検討しましょう。
こちらは、雨漏りや基本構造部の瑕疵が見つかったときに補修工事費用を保険金で賄ってもらえるという利点もあるので検討する価値はあります。
但し、現場検査を実施した結果、耐震診断と同様に不適合と判断されることが多いです。半数以上が不適合と判定されており、築年数が古いものほど不適合の確立が高くなっています。
木造住宅なら、耐震診断と既存住宅売買瑕疵担保責任保険の検査を同時に実施してもらうと効率がよいのでお勧めです。アネストでは、ホームインスペクション(住宅診断)に既存住宅売買瑕疵担保責任保険の検査を網羅しているので、ホームインスペクションと一緒にするとよいでしょう。
引渡し前に手続きすべき
住宅ローン控除を受けるためには、耐震基準適合証明書でも既存住宅売買瑕疵担保責任保険の付保証明書でも、引渡しを受ける前に手続きを進めておかなければなりません。
耐震基準適合証明書の場合は、耐震診断を引渡し前に実施して不適合であった場合、引渡し後の耐震改修・補強工事を適切に行うことで、住宅ローン控除を受けられることもあります。ただし、引渡し後の耐震診断ではこれもできません。
いずれにしても、引渡し前に手続きを進める必要があることを理解しておき、売買契約を締結する前後のできるだけ早いタイミングで耐震診断等の取り扱い業者へ相談しておきましょう。もちろん、アネストではこれに対応しているのでいつでもご相談ください。
これらを検討すべきタイミングは、「中古住宅の購入・引渡しの流れと注意点」で購入の流れとともに解説しているのでわかりやすいでしょう。
前述のとおり、2022年(令和4年)度の税制改正により、建物の登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であれば、耐震基準適合証明書や既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書がなくても住宅ローン減税を受けられることになりました(追記:2022年4月1日)。
執筆者

- 編集担当
- 2003年より、第三者の立場で一級建築士によるホームインスペクション(住宅診断)、内覧会立会い・同行サービスを行っており、住宅・建築・不動産業界で培った実績・経験を活かして、主に住宅購入者や所有者に役立つノウハウ記事を執筆。