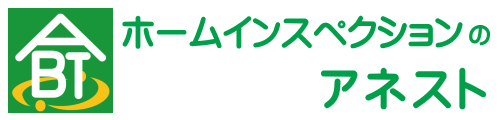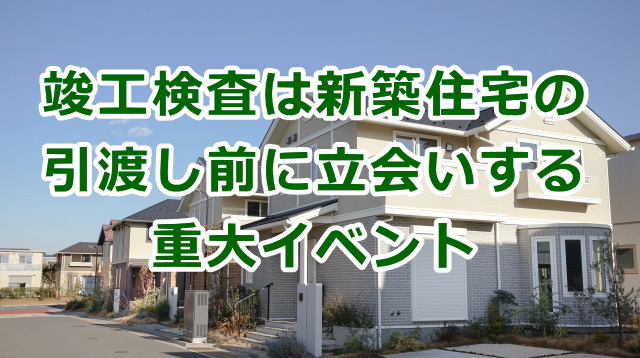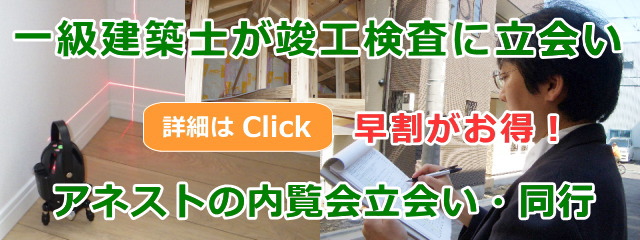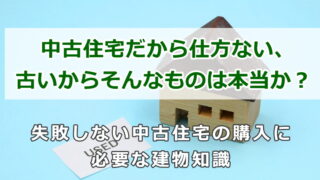新築一戸建て住宅(建売住宅)を購入、または注文建築の家を建てたとき、その住宅の完成後、且つ、引渡し前に行われる大事なイベントが竣工検査です。
この竣工検査について正しく把握していないまま、住宅の引き渡しを受けてしまい、入居後に様々な建物の不具合に気づいた人から後悔した話を聞くことも多いため、新築住宅を買う人ならきちんと学んでおきたいテーマです。
この記事では、新築住宅の竣工検査の基礎知識とその重要性、専門家による立会いについて解説しています。できれば、引渡し前に学んでしっかり対策をとっておきましょう。なぜなら、竣工検査は失敗が許されない大事なイベントだからです。
新築住宅の竣工検査とは?
新築住宅における竣工検査とは、何かについて解説します。
竣工とは
まず、竣工とは、基本的には建物の完成のことを指しています。
物理的に住宅が出来上がった状態を完成と言い、建築会社や分譲会社(売主)がそのプロジェクトの完了を宣言する意味で竣工と言うように使い分けていることもありますが、住宅・不動産業界や一般消費者向けにおいて、明確に使い分けず、同じ意味で用いていることが多いです。
また、建築会社によっては、建物本体だけで竣工と言っていることもあれば、外構工事など受注した工事全ての完了をもって竣工と言っていることもあるため、「竣工の予定日が12月下旬です」などと説明を受けた時に、建物本体だけのことなのか、外構工事などの完了も含めて話しているのか突っ込んで聞いておく方がよいでしょう。
なお、竣工日(=完成日)は、契約書で確認できます。注文住宅の場合は工事請負契約書で、建売住宅の場合は売買契約書で確認してください。多くの契約書のひな形において、竣工日は書面の前半部分に記載されています。
もし、記載箇所を見つけられないときは、建築会社や不動産会社に聞いてみてください。
竣工検査とは
次に竣工検査の説明です。
建物が竣工した直後に、施工不具合がないか、および契約したとおり(図面どおり)に建てられているか確認するために行う検査を竣工検査と言います。
完成検査という言葉がありますが、これも基本的には同じ意味で使われていることが多いです。
建てた建築会社が自社検査として行う竣工検査、工事を発注した施主が行う竣工検査、さらには住宅の買主が行う竣工検査もあります。
建てた建築会社が行うもの
その建物を施工した建築会社が行う竣工検査は、自社検査や社内検査と呼んでいることが多いです。これは、その住宅を注文した人や買主に住宅を最終確認してもらう前に、自社チェックして、補修すべき箇所を是正対応するためのものです。
自社検査は、本来ならば、建築会社が当然に行うべきものですが、そういった意識が不足している会社では行わないこともありますし、工事遅延によって引渡し日までにスケジュールの余裕がなくて、その機会を設けなかったという事例もあります。
工事の発注者が行うもの
工事の発注者(注文者)とは、注文住宅の家であれば、最終消費者である施主です。そして、建売住宅であれば、その物件の売主となる不動産会社です(不動産会社が工務店に工事を発注するので発注者となります)。
不動産会社が販売する建売住宅においては、その不動産会社が建設業も兼ねていることも多く、その場合は工事種別ごとに様々な下請け業者に工事を発注しています。
また、不動産会社が建築工事一式を建築会社に発注して、自社では何も工事や現場管理をしていないケースもあります。このケースでは、本来ならば工事の途中や建物完成時などのタイミングで発注者として検査すべきですが、何もしないで下請けの建築会社に任せきっていることも少なくありません。つまり、工事も検査も下請けに丸投げということですね。
いずれにしても、工事を発注して完成した後に、発注者(注文者)が施工状態などをチェックするもので、発注者は施主とも言うため、施主検査とも言います。
ただし、施主検査という言葉は、常に竣工時の検査を指しているとは限りません。建築途中でも施主による検査を行うことがあり、それも施主検査と呼ぶことがあるためです。
住宅の買主が行うもの
建売住宅の買主が、引き渡しの前に行う検査も竣工検査です。
建売の場合、売買契約の時点で既に建物が完成済みのケースもあれば、未完成(着工前や建築途中)のケースもありますが、いずれのケースであっても建物完成後・引渡し前のタイミングで買主が行うものが竣工検査です。
竣工検査と内覧会は同じか?
竣工検査のことを内覧会と呼ぶことも多いです。これは、基本的には、一般消費者が行う建物完成後の検査の機会を指しており、注文建築の家なら施主が行うもので、建売住宅なら買主が行うものです。
つまり、内覧会と竣工検査が完全に一致するとは言えませんが、一般消費者が行うものであれば、内覧会のことだととらえて問題ありません。
ただし、建築会社や不動産会社によっては、内覧会ではなく、確認会や引渡し前の立会いなどと別の名称を使っていることもあるので、注意してください。
竣工検査と完了検査の違い
竣工検査と似た言葉で完了検査というものがありますので、ここで説明しておきます。
完了検査とは、建物の建築工事が完了した段階で行うものとして、建築基準法の第7条で規定されている検査のことです。工事完了後、且つその建物が使用される前に、自治体や国交省の指定確認検査機関によって行われるもので、合格すれば検査済証が発行されます。
この検査では、予め申請されていたとおりに、建築基準法の規定を守って建築されているか確認しています。
完了検査を受けているなら、建物に施工不具合などの問題が無いと誤解する人がいますし、そのように消費者に説明しているハウスメーカー等の営業担当者もいますが、多くの場合、5~20分くらいの短時間で簡易的に現場確認している程度であり、そもそも施工精度の確認は目的となっていないので、誤解しないようにしましょう。
竣工検査と完了検査の2つを混同してしまう人も少なくないので、比較表を作りました。この表で確認すると、竣工検査と完了検査の違いがわかりやすいです。
| 項目 | 竣工検査 | 完了検査 |
|---|---|---|
| 目的 | 施工不具合の有無や契約通り(図面どおり)に完成しているか確認するため | 建築基準法の規定を守っているか確認するため |
| 実施する者 | 建築会社、発注者(施主)、買主 | 自治体や国交省の指定確認検査機関 |
| 実施時期 | 建物完成後、引き渡し前の間に行う(引き渡し日の10日以上前を推奨) | 建物完成後4日以内に建築主が申し出て、それから7日以内に行う |
| 調査範囲 | 検査時に目視できる範囲の全て | 検査時に目視できる範囲で、且つ建築基準法の規定にかかわる部分 |
| 所要時間 (建物面積 100平米の場合) | 40~60分程度 (ただし、専門家に依頼すると2~2.5時間程度) | 5~20分程度 |
竣工検査と施主検査の違い
完了検査以外にも竣工検査と似た言葉があり、それは施主検査です。竣工検査と施主検査の違いがわからないという声も少なくありませんので、説明します。
ちなみに、施主検査は「せしゅけんさ」と読みます。また、新築住宅の工事における施主とは、工事の発注者のことです。
竣工検査が、建物の完成後に行うという「時期」を指しているのに対して、施主検査は施主が行うという「誰が行うか」を指しているという違いがあります。
施主検査が最も多く実施されているのは、建物完成後ですので、竣工検査と同じですが、建築途中にも実施することがあるため、完全に一致しているわけではありません。
一方で、竣工検査は施主以外に建築会社や建売住宅の買主が行うこともあります。
少し複雑ですね。こちらも比較表を用意しました。
| 項目 | 竣工検査 | 施主検査 |
|---|---|---|
| 目的 | 施工不具合の有無や契約通り(図面どおり)に完成しているか確認するため | 施工不具合の有無や契約通り(図面どおり)に施工しているか確認するため |
| 実施する者 | 建築会社、発注者(施主)、買主 | 発注者(施主)のみ |
| 実施時期 | 建物完成後、引き渡し前の間に行う(引き渡し日の10日以上前を推奨) | 建築途中や建物完成後 |
| 調査範囲 | 検査時に目視できる範囲の全て | 検査時に目視できる範囲の全て |
| 所要時間 (建物面積 100平米の場合) | 40~60分程度 (ただし、専門家に依頼すると2~2.5時間程度) | 20~40分程度 (ただし、専門家に依頼すると1~2時間程度) |
竣工や竣工検査の言葉の意味・内容を正確に理解するだけでも、これだけの情報があるので、少し複雑ですね。
もし、建築会社から内覧会や竣工検査などの名目で案内があれば、消費者が行う大事な検査のことだと理解し、ただのお披露目会として終えず、きちんと施工不具合の有無などをチェックするようにしてください。
竣工検査の調査範囲とチェックポイント
竣工検査でチェックするべきポイントや調査範囲を解説します。
調査範囲
竣工検査の際に調査できる範囲は、建物完成状態で目視できる範囲と手が届く範囲です。
逆に言えば、目視することができない壁内や基礎コンクリート内部は調査することができません。
ただし、床下や小屋裏(屋根裏)は、点検口があり内部へ安全に進入できるならば、調査することができます。
チェックポイント
竣工検査におけるチェックポイントはいくつもありますので、「契約通りか(図面どおりか)確認」「建物の施工状況のチェック」の2つに分けて紹介します。
契約通りか(図面どおりか)確認
契約通りの建物であるかチェックするのは、竣工検査の大事な目的の1つです。契約どおりとは、契約の対象となる図面の通りか確認するということです。
建物の形状、大きさ、使用された材料・設備などを確認したいところですが、現実的には材料の1つ1つを確認することは非常に困難なため、可能な範囲で行うことになります。
注文建築の家ならば、施主から指定して注文したものも多いでしょう。そういった物が指定したとおりであるか確認するのです。
- キッチン・トイレ・風呂・洗面台などの住宅設備(水栓なども)
- 床・壁・天井の仕上げ材
- 外装材(外壁・屋根の仕上げ材など)
- 室内扉・窓・玄関扉・勝手口の扉
- 階段
- 収納・棚
- 点検口
- 照明(ダウンライトなど)
- コンセント
- スイッチ
- 外構(カースペース・境界フェンス・外部照明・外部水栓など)
注文したとおりの商品であるかをチェックするだけではなく、その位置やサイズも確認するようにしてください。
建物の施工状況のチェック
もう1つ大事な確認対象となるのが、施工不具合がないかという点です。簡単に言えば、欠陥住宅になっていないか確認するということです。
- 床・壁・天井の仕上り
- 床や壁の傾斜
- 構造耐力上支障がある基礎のひび割れ
- 防水上の懸念がある外壁やバルコニー周りの隙間・ひび割れ
- 床下の断熱材・配管・床組み(構造金物を含む)・基礎
- 小屋裏(屋根裏)の断熱材・小屋組み(構造金物を含む)・野地板
- ユニットバスの天井点検口の内部(ダクト・配線など)
上に挙げたチェックポイントは、構造耐力や建物の基本性能に関わる大事な点ですが、傷や汚れについても気になるものは指摘して、補修などの対応をお願いしてください。
竣工検査で失敗しないための知識と注意点
注文建築の施主、もしくは建売住宅の買主が、引き渡しの完了後に失敗したと思ったり、後悔したりしないために、新築住宅の竣工検査について知っておくべき基礎知識と注意点を解説します。
完成・竣工検査・引き渡しの流れを把握する
建物が完成するともうすぐ新居に入居できるので、新生活への期待もあってワクワクした気分になる人も多いでしょう。しかし、その前に大切なタイミングなので、注意して取引を進めてください。
注意点を理解するためにも、まずは竣工検査や引渡しの前後における一般的な流れを把握しておいてください。それは、以下のとおりです。
建物完成から引き渡しの流れ
- 建物完成
- 竣工検査(内覧会とも言う)
- 補修工事
- 補修後の確認
- 引き渡し
- 入居(引っ越し)
上のような流れで取引を進めていく予定となっているか、建築会社や不動産会社に確認をとっておきましょう。
竣工検査のタイミングに要注意
一般的な取引の流れを把握したところで、次に竣工検査のタイミングについて注意点を紹介します。
新築住宅の竣工検査を行う適切なタイミングは、建物が完成後、引渡しを受けるまでの間です。そして、遅くとも引渡し日の7日前まで、理想は14日前までには行っておきたいものです。
7日以上前の竣工検査をお勧めする理由は、以下の2点です。
- 検査で施工不具合等を指摘した後、その補修と補修完了後の現地確認を済ませてから引渡しを受けることが最も良い取引の流れであること
- そのためには、少なくとも7日以上、できれば14日以上の日数が必要であること
検査の結果、補修やその後の現地確認まで3日程度で実施できることもありますが、それはやってみるまでわからないことなので、後悔することのないように、ゆとりをもったスケジュールを組んでおくことがお勧めします。
補修後の確認方法
竣工検査で指摘した事項について補修してもらった後の状況は原則として現地で目視確認することをお勧めします。現地で実際に見ながら、建築会社等から説明を受けて確認するのが一番わかりやすいからです。
しかし、何らかの事情により、補修後の状況を現地で確認できないときがあります。たとえば、対象物件から遠方に住んでいて時間的にもコスト的にも何度も現地訪問できない人や、引き渡し日との兼ね合いで平日しか現地確認できる日がないけど仕事を休めない人です。
このようにどうしても現地確認できないときは、建築会社等に補修後の状況を確認できる写真を提出してもらって確認する対応方法も考慮してください。写真で判断しづらいこともありますが、何もしないよりは参考になりうるでしょう。
建物の完成後に竣工検査を行うべき
竣工検査というくらいですから、当然ながら、建物が完成してから行うべきです。完成状態で施工不具合などの問題がないか確認するためですから、本来ならば当たり前のことであり、これは建築会社も理解しています。
理解しているはずなのに、工事が大きく遅延したとき、前述の「建物完成から引き渡しの流れ」のとおりに進めると引き渡しも遅れてしまうという理由で、建物完成の前に竣工検査を行いたいと建築会社から案内されることがあります。
しかし、これを買主(注文住宅なら施主)が受け入れてしまうと、未完成部分や養生シート等で隠れて見られない箇所をチェックできないことになり、買主にとってデメリットが大きいです。
きちんと建物が完成してから、竣工検査を行うようにしてください。未完成状態で実施したいと案内されても、完成後に行うよう明確に意思表示すべきです。
引き渡しは、必ず建物が完成後にすべき
工事が遅延すると竣工検査の時期だけではなく、引き渡し日にも影響することがあります。建物の完成が予定より大幅に遅れると、引き渡し日も延期せざるを得なくなるというわけです。
しかし、一部の取引において、完成していないにも関わらず、住宅の引き渡しを受けてしまい、その後の工事が雑だったり、必要な補修工事をしてくれなかったりというトラブルに直面し、後悔している人もいます。
建築会社が引渡しを急ぐ理由
建築会社が完成前に引き渡したいと考えるのは、決算期や月末の締めに際して、会社の業績や担当の営業成績を達成するために必要だと判断したときで、買主側が拒否しても引き渡しを強行するケースまであり、注意が必要です。
買主が引渡しを急ぐ理由
買主が完成前に引き渡しを受けたいと考えるのは、早く入居する必要があるときです。たとえば、自宅の退去期日が迫っているときなどに起こっています。
理由が何であっても、買主側のリスクが小さくないので、引き渡しは完成後とすべきです。
引っ越し日のスケジュールにゆとりが必要
工事が遅延することは、建築業界ではよくあることで、1ヵ月以上も完成時期が遅れてしまう住宅もあります。その理由にもいろいろあり、職人・現場監督などの人手不足や建築資材・住宅設備などの納入遅れなどです。
工事遅延により、完成日や引き渡し日が延期になっても柔軟に対応できるようにするため、事前に対処しておく必要があり、その方法は引っ越し予定日を引き渡し日の直後としないということです。
ただし、家賃と住宅ローンの支払が重なる期間が生じたとしても最小限にしたいのは当然ですから、工事の進捗をまめに確認しながら日程調整するとよいでしょう。
完成から竣工検査、引き渡しの流れのところは、本当にトラブルが多い時期なので、十分に注意してください。
竣工検査に必要なもの
初めての竣工検査で慣れないことも多いでしょう。まずは、当日持参するものを準備することからはじめたいものです。持参すべきものは以下のものです。
- 筆記用具(ペン・メモ用紙など)
- 間取り図(指摘箇所は間取り図に記録するとわかりやすい)
- デジカメまたはスマホ(大事な指摘箇所を撮影するため)
- メジャー(採寸のため)
- 懐中電灯(床下や屋根裏のチェックのため)
- スリッパ(冬場は寒い)
筆記用具や間取り図は、現地で不具合等を指摘した事項をメモするときに使います。
スマホのカメラ機能やデジカメは、指摘箇所を撮影して後で確認しやすくするために使います。
メジャーは、家具・カーテン等の設置を考慮して、竣工検査のときに採寸しておきたいなら用意しておきましょう。入居までのスケジュールにゆとりがあるなら、引き渡し後にゆっくり時間をとって採寸しても問題ありません。
懐中電灯は、床下や屋根裏、天井裏を確認するときに必要です。スマホのライト機能でも構いません。
スリッパは、冬場の床は冷たくて大変なので、準備をおすすめします。ただし、建築会社側で用意していることもあります。
竣工検査に立会う人
竣工検査の当日に誰が立会う人が誰であるか紹介します。
| 関係者 | 一般的な立会い有無 | 立会いの重要度 |
|---|---|---|
| 買主(または施主)※消費者 | 有り | 高い |
| 建築会社 | 有り | 高い |
| 売主(建売住宅の場合) | 有り | 高い |
| 不動産仲介業者 | 有り | 普通 |
| ホームインスペクター | 任意 | 高い |
消費者である買主や施主が立ち会うのは当然で、建物の状況を把握するためにも重要度は高いです。むしろ、消費者が確認するために設ける機会です。
建築会社は、消費者から指摘を受けたり、質問等に回答したりするために立ち会うべき立場です。しかし、建売住宅では、立会いしないケースも少なくありません。
建売住宅における売主は、買主に対する責務があるので、当然に立ち会うべき立場です。しかし、建築会社(工務店)に立会いを任せていて、立ち会わない業者もいます。
不動産仲介業者は、その仲介により対象物件を購入したときにのみ立ち会う立場です。補修すべき点などの指摘事項は、建築会社か売主に現場で直接伝えられる状況ならば、仲介業者はただ立ち会うだけなので、重要度は低いと言えます。
ホームインスペクターは、施工不具合の有無をチェックしてもらうために、消費者が竣工検査に立会いを依頼するインスペクション業者のことです。この依頼は任意ですが、専門知識と経験・ノウハウをベースとしたホームインスペクション(住宅診断)の有効性が高いことから、依頼する人が多くなっています。
新築の引き渡し前に行う竣工検査へ専門家が立会い
注文建築の施主、もしくは建売住宅の買主の皆さんから、「竣工検査に立ち会って欲しい」とご依頼をいただくことがよくあります。施工不具合の有無を自分たちだけで見抜くことは難しく、建築の専門知識・経験が問われるだけに、専門家へ同行依頼するニーズは多いです。
専門家に竣工検査に立ち会ってもらうことについて、詳しく知らなかったという人向けに、これを解説します。
本記事を執筆しているアネストでは、2003年から竣工検査の立会いを行っており、実績が豊富です。その竣工検査立会いの内容を説明します。
竣工検査立会い = 内覧会立会い・同行
新築住宅の完成後、引渡し前の立会いサービスのことを、アネストでは「内覧会立会い・同行(竣工検査・完成検査)」と名付けています。施主や買主が行う竣工検査を内覧会と呼ぶことが多いことに由来しています。
施主(または買主)だけで、確認できないこと、判断できないことまで、専門家が代わりに調査し、施工不具合があれば指摘してくれるサービスで、大事な住宅に対する安心感を得るために役立つとされています。
チェックポイントは270箇所超
竣工検査で確認するチェックポイントは、270箇所超もあります。
その範囲は、建物外部の基礎・外壁・軒裏・屋根、外構工事(フェンス・塀・駐車場等の土間コンクリートなど)、建物内部の床・壁・天井・建具・設備など多岐にわたりますが、簡単に言えば、目視できる範囲の全てが対象となります。
新築住宅で見つかる施工不具合は、建物外部(基礎・外壁)や床下、屋根裏で見つかることが多いです。どこに、どのような施工不具合が多いか理解して代わりに診断してもらえることは、大きなメリットになっています。
仕様レベルの確認ではない
誤解してはいけないこととして、一般的に第三者の専門家(ホームインスペクター)が行う検査の目的は、施工不具合の有無の確認であって、仕様レベルの良し悪しを確認や、構造・機能面で影響のない細かな傷チェックではないという点です。
仕様レベルは、売主と買主、または施主と請負者が事前に、互いに取り決めておくべきものであって、第三者が後から勝手に決められるものではないからです。「もっと良い材料を使ってください」などとは言えないわけです。
また、構造や機能面で問題のない細かな傷や汚れなどは、美観上の問題があるかもしれませんが、そういった問題に第三者が明確に適否を判断できるものでもありません。ただ、施主や買主としては、気になる箇所を建築会社などへ指摘して可能な範囲で対応してもらうことを否定するわけでもありません。
一級建築士で住宅の設計・監理の経験も豊富なものが立ち会う
新築住宅の竣工検査ですから、必要な経験は新築住宅の設計や監理です。商業ビルやマンションの経験がいくら豊富でも一戸建て住宅の経験がなければ、担当すべきではありませんね。
一級建築士であることは、アネストでは最低基準の1つですが、経験内容・質も最低基準の1つです。マニュアル・チェックリストもありますが、それだけで対応しきれるものではありません。
立会いの所要時間
新築住宅の竣工検査は、一般の人だけで行うと1時間もかからずに終えてしまうことが多いです。これは、チェックポイントがわからない、もしくはポイントをわかっても味方や判断の仕方がわからないからです。なんとなく見てすぐに終わってしまうわけです。
専門家が行うときは、100平米・2階建ての住宅で、2~2.5時間くらいです。床下や小屋裏(屋根裏)の内部の調査(オプション)もつけると3.5時間くらいです。規模や指摘事項の量、建物プランなどによっては、4時間を超える現場も少なくありません。
調査項目・チェックリスト
専門家が見ているチェックポイントの具体的な内容は気になりますよね。ここで項目名を列挙すると大変な量になりますので、別紙(アネストへ依頼したときに提出される報告書のサンプルPDF)にて確認できるので、ぜひご覧ください。
以上、新築住宅の引き渡し前に行われる竣工検査や竣工検査への立会いについて、解説しました。
引き渡しを受ければ、その住宅の所有権があなたに移ります。それ以降は、多くのことが自己責任にもなりますし、引渡し時に売主や建築会社へ代金を支払った後は、対応が悪くなってしまう業者もいることから、引渡し前の竣工検査が大事なのです。
その大事なタイミングを無駄に過ごすことのないように、しっかりした対策をとって竣工検査にのぞみましょう。できれば、専門家に立会い依頼して安心を得ることも検討しましょう。
執筆者