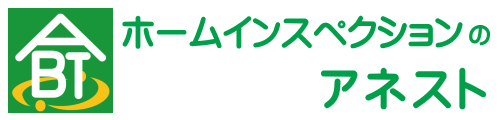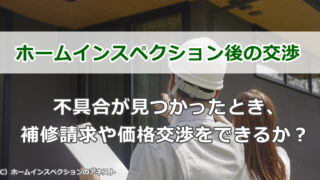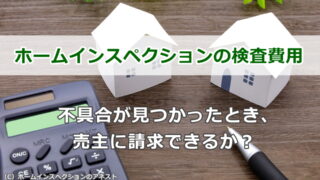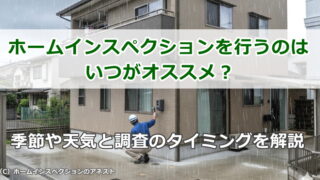購入しようとした新築住宅、もしくは注文建築で建てようとした住宅について、ハウスメーカーや不動産会社の担当者から、型式適合認定工法の住宅だと説明を受けたけれど、どういう意味なのかわからないという人は多いでしょう。
実は、中古住宅を購入するときに、同じように仲介業者から説明を受けることもあります。
しかし、「国に認定された工法で建てた家だから安心」などと言われても、それが本当かどうか建築知識のない人に判断するのは容易ではありません。
そこで、一般の人にとって謎の多い型式適合認定の住宅についての基礎知識とこの住宅に第三者のホームインスペクション(住宅診断)を入れるべきかどうかについて解説します。
型式適合認定工法の住宅の基礎知識
どのハウスメーカーであっても、その会社の標準的な仕様があるものです。大手になれば、標準的な仕様が複数の場合もあります。この標準的な仕様で建築する住宅の型式について一定基準に適合していると認定を受けているものが、型式適合認定です。
ここでは、住宅を購入する人が知っておきたい型式適合認定を得た工法の住宅に関する基礎知識を解説します。
型式適合認定とは?
住宅の型式適合認定は、国土交通大臣より指定を受けている認定機関が、建築基準法に基づいて審査して実施しています。
そのため、型式適合認定を受けた住宅の工法のことを単に認定工法と呼んでいることも多いです。ハウスメーカーや不動産会社から、認定工法の住宅だと説明を受けた場合は、型式適合認定された工法による住宅だと理解してほぼ間違いありません。
型式適合認定ではない住宅との違い
住宅を建築する際、通常は、設計者が個々の建物構造の安全性を検討したうえで、建築基準法に基づく建築確認申請を行います。同じような建物プランであったとしても、都度、検討して建築確認申請をして、確認検査機関による確認を受けなければなりません。
これに対して、型式適合認定の工法の住宅の場合、構造やその他の基準について認定を受けているため、この点における確認が簡略化されます。いろいろな建物プランであっても、 建築確認の申請や検査を簡素化できるのです。
このように簡素化できることが、ハウスメーカーのメリットの1つと言えます。
建築設備にも型式適合認定がある
型式適合認定といえば、住宅の構造に関わる工法がイメージされがちですが、実は、エレベーター、浄化槽、防火設備、換気設備なども型式適合認定を得ることができます。このことは、消費者が説明を受ける機会が少ないので、意識せずに利用していることが多いです。
大手ハウスメーカーの家は型式適合認定が多い
大手ハウスメーカーは、型式適合認定を受けている住宅が非常に多いです。逆に、小さな工務店の全てや中規模の住宅メーカーのほとんどは、この認定を受けていません。この認定を受ける手続きが大変だという面もありますが、中小の会社には建築確認申請を簡略化するスケールメリットがないことも理由と言えます。
大手と中小では、供給棟数が大きく異なりますね。
但し、大手ハウスメーカーでも全ての住宅がこれに該当するわけではありません。同じメーカーの住宅でも、認定を受けているものと受けていないものがあるので誤解しないでください。
軽量鉄骨造(ハウスメーカーによるプレハブ住宅)は型式適合認定住宅
大手ハウスメーカーが建築する住宅には、軽量鉄骨造と言われる構造のものが多いです。これは、プレハブ住宅と言われることもありますが、この住宅は基本的に型式適合認定です。
主なメーカーとしては、積水ハウスや旭化成(へーベルハウス)、大和ハウス工業、セキスイハイム、ミサワホーム、パナソニックホームズがあげられます。
但し、これらのメーカーは、軽量ではない鉄骨造や木造などの住宅にも対応しているため、会社名で構造・工法を決めつけないことも大事です。そして、軽量鉄骨造以外のものでも、型式適合認定工法であるケースもあります。
中古住宅なら耐震診断が難しいというデメリットがある
中古住宅を購入する人や購入した後の人が、耐震診断を希望するケースがよくありますが、型式適合認定の住宅では、最もよく利用される一般診断法による耐震診断ができないため、その時点における耐震性の把握が容易ではないというデメリットがあります。
建築したメーカーに相談したいところですが、快く、そして速やかに対応してもらえないケースが多く確認されており、耐震診断をしたいというニーズのある人にとって1つの障壁になっていると言えます。
型式適合認定を受けた住宅のホームインスペクション
アネストでは、第三者の立場で一級建築士によるホームインスペクション(住宅診断)をしていますが、依頼者から「ハウスメーカーの建てた家でもホームインスペクションは可能か?」「認定方法でも対応できるか?」と問合せを受けることがよくあります。
型式適合認定住宅でもホームインスペクションは可能
結論からいえば、型式適合認定を受けた住宅でもホームインスペクション(住宅診断)をすることは可能です。実際に利用する人も多いです。
新築の完成物件や中古住宅では、基本的には目視できる範囲などに対象範囲・項目は限定されるものの、建物の構造・工法に関わらず対応できるわけです。そして、建築途中の住宅であっても、第三者検査に入ることは可能です。
依頼する前に理解しておくべきことは、ホームインスペクションでは、施工不具合や著しい劣化の有無を調査するものであり、工法の審査をしているわけではないという点です。
建築中の主な検査項目
建築途中の住宅検査(ホームインスペクション)の依頼を検討している人から、どのような項目の検査ができるのか質問を受けることも多いです。
ハウスメーカーから、「オリジナルの工法だけに外部の者が検査できない」「工場で生産しているため、現場で検査することがない」などと言われることがあるでしょう。確かに、型式適合認定の住宅の場合、従来から多く見られる木造在来工法と同じ項目の検査をできるわけではありません。
しかし、木造在来工法ほどではありませんが、検査しておきたい項目はいくつもあります。以下がその一例です。
- 基礎配筋検査
- 基礎コンクリート打設時の検査
- 基礎コンクリートの仕上り
- 構造躯体(壁・床パネル等)の検査
- 防水工事(外壁の目地やサッシ周り等)の検査
- 断熱工事の検査
- 設備配管、電気配線の検査
- 下地材等の検査
- 竣工検査(完成検査)
これらの検査項目は、対象住宅の工法・建物プラン・工程(工事スケジュール等)によって左右されることですので、全てに共通ではありません。これらの検査を念頭に置きながら、設計図や工程表を確認して適切な検査項目や検査のタイミングを決めていくべきです。
これを依頼者が一人で決めることは困難ですから、検査担当の建築士と打ち合わせるなどして決めていくとよいでしょう。
工場生産していることを理由に検査することがないと言いながらも、実際にはまだまだ現場で作業する部分も多いですし、実際に施工ミスが起こることもあります。あくまでも、木造在来工法に比べれば現場で確認する項目が少ないというイメージでとらえておいた方が現実に合ったものです。
ここまで見てきてわかるように、大手ハウスメーカーの型式適合認定住宅であっても、ホームインスペクションを入れる意義があることがわかるでしょう。
関連記事
執筆者

- 編集担当
- 2003年より、第三者の立場で一級建築士によるホームインスペクション(住宅診断)、内覧会立会い・同行サービスを行っており、住宅・建築・不動産業界で培った実績・経験を活かして、主に住宅購入者や所有者に役立つノウハウ記事を執筆。