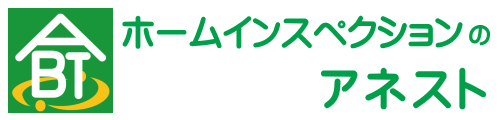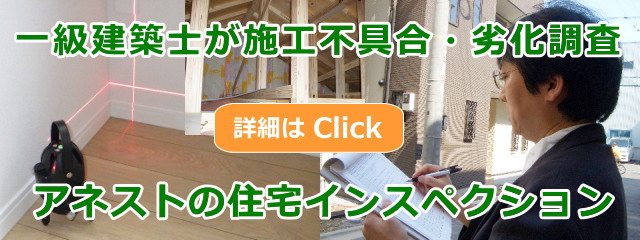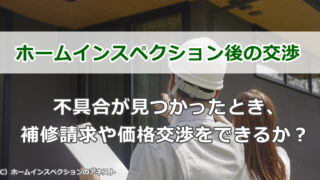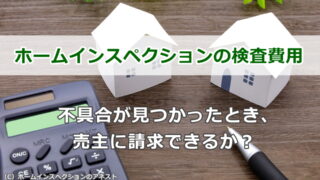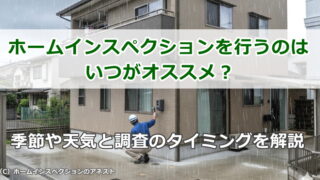日本では、3階建ての住宅を見かけることが多いですね。東京や大阪などの都会で多く見られますが、地方都市でも3階建て住宅は少なくありません。3階建てのなかでも、狭小住宅と言われる建物は、東京や大阪などの都市部で多いです。
3階建ての狭小住宅を購入しようとする人から、「細くて高い建物だけど大丈夫か?」「狭小住宅はよくないと聞く」といった話を伺う機会は少なくありません。その一方で既に大量に供給されている住宅でもあり、住宅購入者にとっては選択肢の1つとなっているのも事実です。
3階建ての狭小住宅の購入を検討している人向けに、その基礎知識やホームインスペクションを依頼する前に理解しておくべきことを解説します。
3階建ての狭小住宅とは?
狭小住宅とは、その文字通り狭い敷地に建築した住宅のことです。狭い敷地がどのくらいなのかという点は、人によって意見も異なりますが、概ね20坪(=約66平米)程度以下をイメージすることが多いです。3階建ての狭小住宅のことを不動産業界ではペンシルハウスと呼ぶ人もいます。細長い形状が鉛筆を連想させるわけです。
この建物の規模感をイメージできますか?
たとえば、60平米の土地に、建ぺい率が60%で、建物の水平投影面積が36平米です。3階建てにすれば、上限で108平米です。容積率が200%だとすれば、延床面積は120平米までですから、条件をクリアしていますね。
これが狭小住宅のイメージですが、もっと小さな住宅も多いことは、SUUMOやHolmesなどの不動産ポータルサイトで物件探しをしている人なら実感していることでしょう。最近では、100平米未満の3階建て狭小住宅が多い印象です。
都市部に多い
3階建ての狭小住宅は、明らかに都市部に多いです。その理由は、都市部は土地価格が高いため、敷地面積を抑えた街づくりとなっている地域が多いからです。もともと200平米程の土地の物件でも、不動産会社が開発して、建売住宅として販売するときには、土地を3軒に割っています。よって、狭小住宅は増えていくわけです。
違法建築が多かった
3階建て狭小住宅は、その建築時期によっては、違反建築が非常に多かったです。地域により違いがありますが、2005年頃までは各地で違反建築が横行していて、開発・販売する不動産会社や建築する工務店も感覚が麻痺していたと言えるのではないでしょうか。
多くの場合、建築基準法に基づいて建築確認申請を行っているのですが、完成時に受けるべき完了検査を受けないまま購入者へ売り渡していたのです。
違反内容は様々で、高さ制限・斜線制限・採光などの面で違反になっていることもありますが、建ぺい率を超える建物となっているものも少なくありません。
ちなみに、今の時代、3階建てや狭小住宅と言われているもでも、違反建築の住宅を建てるケースはほぼないでしょう。銀行の融資も受けられないですね。
内装・外装
3階建て狭小住宅は、もっと大きな住宅や2階建ての住宅と比べて、内装材や外装材には大きな違いはありません。仕様グレードは、施主や住宅供給者次第ですから、狭小住宅ならグレードが低いというわけではありませんが、なぜかそう考えている人も多いようです。
グレードは何と比べるかによっても感じ方は異なりますが、3階建てだから、狭小だからということはあまり関係ないでしょう。
建物の揺れを感じやすい
ホームインスペクションという仕事をしているからなのか、建物が揺れて困っているとの相談を受けることがあります。「こんなに揺れるのだから、建物に何か問題があるのではないか」と不安になるようですが、なかには「3階建ての細長い住宅なので、揺れるのでしょうか」と質問されることもあります。
建物の揺れは、地面から伝わる振動によるものと強風(特に台風のような暴風時は顕著)によるものがありますが、実感としては、3階建て狭小住宅では、振動によるものが多い印象です。
3階建て狭小住宅の多くが、住宅密集地に建設されていて、周囲の建物に囲われる形になっている、つまりお互いが風除けになっていることが影響しているのだろうと考えています。
さて、3階建て狭小住宅が揺れやすいかという点については、重心が高くなることから揺れやすいケースは多いです。ただし、地面からの振動の伝わり方は地盤によっても異なるので、同じ建物プランであっても立地による影響差が大きいです。

揺れの根本的な原因が、建物のプラン上の問題や、施工ミスによるものもあり、その原因を特定するのは困難ことが多いです。
3階建ての住宅は耐震性が心配って本当か?
3階建ての住宅は、2階建てに比べて耐震性が低いと考えている人、心配している人も少なくありません。この点について説明します。
設計と施工の問題
基本的には、2階建てでも3階建てでも、設計と施工がしっかりしていたら問題ないはずです。耐震性を考慮して設計し、その設計どおりに、且つ構造的な施工ミスが無く、建てられればよいのです。1つの目安として、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の耐震等級を確認するとよいです。
住宅性能表示制度は義務ではないため、取り入れていない住宅も多いですが、取り入れている住宅なら、耐震等級を確認しましょう。等級は、1~3まであり、3が最上位のものです。
構造計算している安心感
3階建て住宅は、設計段階(着工前)に構造計算という作業をしています。構造計算とは、建物の構造的な安全性、地震、風雨に耐える力を確認する計算のことで、3階建て住宅ではこれをしなくてはなりません。一方で、2階建てや平屋建ての住宅では、建築基準法の特例により、構造計算しなくてもよいため、実際にしていない物件も多いです。
よって、構造計算している3階建ての方が、これをしていない2階建てより安全だと考える業界人は少なくありません。ただし、構造計算していないことだけが理由で、2階建ての方が劣ると考えるのも正しくありません。

違反建築が多かった時代に建築された3階建て住宅では、建築確認申請通りに建築されていないものがあったため、その安全性には疑問がもたれています。
平屋も2階建ても3階建ても施工品質や劣化状態が大事
住宅性能表示制度の耐震等級や構造計算は大事な要素ですが、結局、現場で施工するときに大きな施工ミスがあれば、その効果・メリットをしっかり享受することができなくなります。つまり、最終的には設計も大事ですが、施工もとても大事だということです。
また、築年数が経過した中古住宅においては、劣化状態・メンテナンスが大事です。
そこで、新築時や売買時に行うホームインスペクション(住宅診断)が効果的です。
新築時なら、施工ミスをチェックして、補修(是正)してもらうことで安全性を担保し、中古住宅の購入時なら、購入前に診断して危ない物件を買わないようにするわけです。もちろん、問題点を明らかにした後、適切な補修・メンテナンスをする前提で購入する選択肢もあります。
3階建て狭小住宅向けホームインスペクションの調査範囲に注意
3階建て狭小住宅を購入するとき、ホームインスペクションを利用する人は多いです。その依頼前に、依頼者が知っておくべき注意点を紹介します。
外壁や基礎をあまり確認できないことがある
3階建て狭小住宅は、住宅密集地に建築されていることが多いです。つまり、隣や裏の家と対象物件の建物と建物の間隔が近いわけです。ホームインスペクションでは、建物の周囲をぐるっと回りながら、基礎や外壁などをチェックしていくのですが、この間隔が近すぎると検査員(ホームインスペクター)が建物の周囲に入っていくことができないですね。
たとえば、建物同士の間隔が30cmでは非常に入りづらいですし、無理に入ったとしても屈んだり周ったりできず、調査になりません。
ただし、床下に潜れる建物であれば、基礎は床下側から確認することが可能です。
屋根をほぼ確認できない
3階建ての住宅では、高さ制限との関係により屋根形状において、勾配が緩い建物が多く、地上から見上げても屋根をほとんど確認できないことが多いです。周囲の道路などとの位置関係次第で、少し離れた場所から遠めに確認できることもありますが、勾配が急な2階建てや1階建てに比べると確認しづらいと言えます。
床下・屋根裏調査の実行率が低い
一般的には、床下や屋根裏の内部へホームインスペクターが進入する調査は、オプションになっていることが多いです。なぜなら、物理的に進入できない住宅もあるからです。とはいえ、基本的には大事な床下や屋根裏スペースですので、調査を希望する人が多いです。
3階建て狭小住宅では、高さ制限が影響して、屋根の勾配が緩いものが多いのですが、そのために屋根裏スペース自体が狭すぎて人が進入できないことがあるわけです。全体的な高さ調整のため、床下スペースの高さが低くて床下に入れない住宅もありますが、経験上、屋根裏に入れない住宅の方が多いです。
以上のとおり、3階建て狭小住宅で行うホームインスペクションでは、それ以外の住宅よりも調査範囲がある程度、制限されがちだということを理解しておきましょう。
狭小住宅にホームインスペクションは必要ないか?
前述のとおり、建物外部においては、確認できる範囲が限定されがちなため、ホームインスペクションを利用する必要がないのではないかと迷う人もいるようです。
調査範囲が限定されるとはいえ、それでも道路側の外壁や基礎などを確認することができますし、室内・バルコニー・床下・屋根裏の施工品質・劣化状況や建具等の動作チェックなどをできます。
こういった範囲・部位において不具合が見つかることは多いので、狭小住宅であってもホームインスペクションを行う意義があり、必要性があると言えるでしょう。つまり、インスペクションの利用はお勧めだと言えます。
ホームインスペクションとは、調査時に目視できる範囲において、建物の不具合(施工ミスや著しい劣化など)の有無を確認する住宅業界の専門的サービスです。何もかも全てをチェックできるわけではないことが前提ですが、可能な範囲で診断してもらうことには意義があるでしょう。
執筆者

- 編集担当
- 2003年より、第三者の立場で一級建築士によるホームインスペクション(住宅診断)、内覧会立会い・同行サービスを行っており、住宅・建築・不動産業界で培った実績・経験を活かして、主に住宅購入者や所有者に役立つノウハウ記事を執筆。